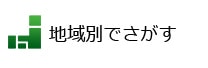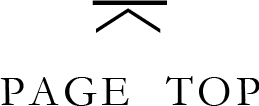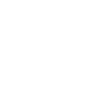日本酒と出汁の相性はバツグン

おでんやさんで時々「出汁割りしましょうか?」というやり取りを耳にしませんか?出汁割りとは、名前のとおり、酒をおでんの出汁で割ることです。出汁だけで飲むと味が濃いので、酒と割ることで穏やかになる。寒い季節にはたまらない楽しみです。
てっちりを食べるときの楽しみがひれ酒だという方も多いと思います。また、蒸留酒にフレーバーを付けたリキュールや洋酒に味を付けて調味し、濃度や温度を調整したカクテル等、お酒の楽しみかたの1つとしての「味変」には自分好みにできる魅力があります。
酒のうま味成分は、主に発酵によってできるアミノ酸や有機酸です。清酒はワインに比べ酸が少ないと言われますが、アミノ酸や有機酸は2倍くらい多くあります。貝などに多く含まれるコハク酸が主体で、生酛造りや熟成酒には特に多く含まれています。うま味の少ない普通酒を出汁で割ることで、うま味を足し、おでんに合う温度と味わいにシンクロさせることで、より美味しくお酒が楽しめるのではないでしょうか。
2大だし定番「昆布と鰹」
出汁は和食のベースとなる大切なもの。その元となる素材は昆布と鰹節です。

うま味の元祖とされる昆布は、グルタミン酸が多く含まれ、特に日高や利尻、羅臼など北海道産が有名で良質とされます。江戸時代、北海道の海岸で天日干しされた昆布は、北前船で西廻りに大阪に入り、そこで加工されることで昆布産業が発達しました。大阪の人がお世話になった北海道の人に塩昆布を贈ったら北海道産の日高昆布だったというような落語があるように、昆布は関西の食文化とは切っても切れない関係になっています。
また、鮮魚の産地でもある富山においては、昆布を活用した保存や調味の工夫がなされ、昆布締め技術が確立されました。北陸地方では他にも、冷涼で乾燥した冬の寒風を活かし、北海道産の棒鱈や昆布などの加工・熟成を行っています。かつて鯖街道を通じて京都に運ばれていたこういった食材は、今もなお京料理の重要な食材として活用され続けています。

次に、鰹節の原料となる鰹は回遊魚で、黒潮に乗って日本近海にやってきます。鹿児島や高知、静岡等太平洋沿岸の港での水揚げ量が多く、奈良時代の延喜式に「堅魚」として記載が残っているように、古来からなじみ深い食材です。「堅魚」ということは、今の鰹節のように固かったのかと思うのですが、奈良時代にはまだ薫製の技術がなかったため、煮て乾燥させただけのなまり節のようなものだったと考えられています。
現在の鰹節は、鰹を三枚に下ろし、釜で煮立て、骨を抜き、燻して乾燥させる。その後天日干しし、カビを付けて削り、燻してからの工程を繰り返し枯節になります。特に良い枯節は油分と水分が極限まで抜かれトパーズのように硬くなり、世界一硬い食材としてギネス認定を受けているほどです。
江戸時代、鰹は水揚げされた漁港の近くで加工され、保存性を高めてから大消費地へ運ばれ、産業として発達していきました。鰹節にはうま味成分であるイノシン酸が多く含まれ、昆布と並び、出汁の重要な材料となります。この昆布と鰹節の相乗効果でうま味が増した美味しい出汁が出来上がるのです。
まだまだある乾物バラエティー 優れた特性とは

かんぴょう、切り干し大根、干し椎茸、木耳、ぜんまい、豆、干し芋。乾物とは、野菜や海藻、魚介等を乾燥させて水分を抜き、雑菌の繁殖を防ぐことで保存性を高めた食品のことです。保存性を高める事が第一の目的だったので、するめやにぼし、ふかひれや干しあわび、干しなまこ等日常的な物から高級な物まで幅広い。特に中華食材は、古くより遠方に運ぶことを目的とされていたためでしょうか、高級乾物のバラエティーが豊かです。
また、流通や価格が安定するなど、常温保存によってもたらされるメリットは他にもあります。湯葉や高野豆腐、麩、春雨等は季節を問わず、しかも美味しく調理しやすい。値段が変動する旬のものと組み合わせることで、コストバランスがとれます。また、ドライフルーツ等は調理する際に使いやすく便利で、乾物は食材における優れた名わき役といえるのです。
乾物には、保存性だけでなく、もう1つ優れた特徴があります。それは、乾燥させることによって、栄養価も増し、さらにうま味も凝縮されることです。例えば、切り干し大根は食物繊維、カルシウム、鉄分が10倍以上、干し椎茸はビタミンDが約8倍にもなります。
天日干しで作ったものがより良いとされるのは、太陽エネルギーが一定に照射されるのではなく、強かったり陰ったりすることによって栄養価が一層高まるからだそうです。戻すときにも天日を当てるとさらに同様の効果があるらしく、乾物の潜在能力には驚かされます。
味の要素「うま味」メカニズムを紐解く

第5番目の味の要素とされるうま味は、減塩につながりヘルシーだと、海外からも注目されています。和食が発達した京都では、野菜や山菜の素材を生かすために色、香りの薄い淡口醤油が使われます。その結果、出汁の香りが引き立ち、おいしさを損なうことなく塩分の摂取を抑えることができるのです。そういった理由で、見た目も美しい和食を取り入れたライフスタイルは海外でも嗜好されるようになり、ますます広がりを見せています。
では、具体的にうま味とはなんでしょうか?1908年に池田菊苗博士が昆布からグルタミン酸を取り出し「うま味」と名付けたのがその始まりで、日本の食卓に欠かせないものと考えられてきました。1985年にはうま味国際シンポジウムが開催され、UMAMIが国際用語になりました(日本うま味調味料協会Webサイト参考(https://www.umamikyo.gr.jp/) ※外部サイトへ移動します)。さらにうま味の科学的研究が進み、そのメカニズムが徐々に明らかにされてきています。
それによると、うま味の主要成分はグルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸で、グルタミン酸は昆布等植物に多く含まれ、イノシン酸は鰹節等魚、肉に多く、グアニル酸はきのこ等に多く含まれています。和食の昆布と鰹の出汁や干し椎茸が良く使われることを思うと確かに頷けます。
2015年ミラノ万博では和食が取り上げられ人気を博し、海外での和食ブームはさらに加熱しているのですが、鰹節はカツオブシカビが付着している理由で検疫に引っ掛かるなど、海外で和食の味を再現するには難しい問題点があります。
しかしながら、うま味の科学的な研究が進んだおかげで、現地で調達できる代用品が開発されてきています。例えば、鰹節の代用品として鶏のむね肉を節にした「鶏節」を、昆布は「ドライトマト」を活用することで、和食の出汁を再現することができるのです。
グルタミン酸はトマトの他玉ねぎ、エシャロット、アスパラガス、ビーツ、チーズなど。イノシン酸は豚肉、牛肉、ベーコン、生ハム、アンチョビなど。グアニル酸は乾燥ポルチーニ、乾燥モリーユなどにも多く含まれており、その土地毎に合った出汁が開発されていけば、和食が国や文化の垣根を越えてさらに進化していくのではないかと期待します。
出汁と乾物を使った酒にあう料理レシピを、次回紹介!!
一番だしは手間がかかるので自宅で作るのはなかなか機会がないと思いますが、一度チャレンジしてみては如何でしょうか。